2023年08月01日
<重要なお報せ>全日赤熊本結成しました!!!
皆さん大変にご無沙汰しております。
まず、このブログに足を運んで下さっている皆さま、大変長らく更新せずにいましたことを謝りたいと思います

更新しない間にあった事を簡単にご報告します。
(交渉議題は年休取得促進や時間外手当申請に関すること、非正規職員の処遇改善、2023年4月の新賃金移行に関して、ハラスメント被害など等です)
他に、ブログを観て下さった方々からご相談も頂いています。
交渉や折衝の結果、権利獲得や病院が職員の為に約束をした事、夏期一時金を昨年より0.1ヵ月増を回答したとかありましたが、ごめんないさい。
 書き切れないため、追々ご報告出来たら良いなと思っています
書き切れないため、追々ご報告出来たら良いなと思っています
このように、いろいろな活動をしていたところ昨年より、組合加入者が増え、より職場改善を進めるため、今年5月下旬に熊本日赤病院内に正式に熊本赤十字病院労働組合を結成する運びとなりました





写真は6月4日に結成レセプションをしたものです。
(組合名)熊本赤十字病院労働組合(通称:全日赤熊本)
(場所)熊本赤十字病院内
(連絡先
 ) zkrchp@gmail.com
) zkrchp@gmail.com(院内窓口)臨床工学部組合担当者
(臨床工学部に来所頂き、スタッフに組合の担当者さんをお願いしますとお声かけ下さい)
職員の皆さんには、是非組合加入をして、ご一緒に職場をよくする活動に参加して欲しいです



『加入はちょっと...けど話は聞いてみたいor働いていて疑問に思う労働条件の事を聞いてみたい』方はいつでもお気軽に院内窓口までご訪問下さい

直接訪問を躊躇される方は匿名でメールをお送り頂いて構いません

お待ちしています

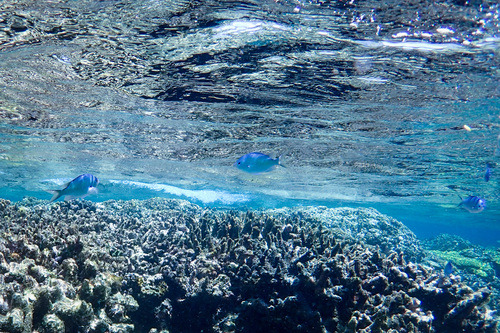
2018年12月14日
年休5日の義務化について
日本政府は「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章(2007年)」と「仕事と生活の調和推進の ための行動指針」において、2020 年までの年休取得平均目標値として、取得率を 70%とすることが掲げられています。
これは先進諸国の中でも日本において極端に年休取得率が低いことに起因し改善の必要性が迫られた背景もあります。
しかし目標数値を掲げたものの実態として年休取得率がほとんど伸びていないことから、実質的な数値を上げるために来年4月1日から企業に対し雇用する職員に年休5日取得を義務化することが決定しました。
ちなみに日本赤十字社の場合、2017年(H29年)全体平均は8.1日です。
厚労省の「平成 29 年就労条件総合調査」(平29.12.29)によると、平成 28 年(又は平成 27 会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数によると、企業規模1000人以上の職場は平均55.3%の取得率です。
この調査の数値を日本赤十字社に当てはめると21日×55.3%=平均11.6日となります。なので取得率は日本赤十字社全体平均値38.5%(平均8.1日)は同規模企業と比べても3日程度低い現状にあります。
この政府の掲げる年休取得70%を日赤職場で実現するには15日(14.7日)/年取得する必要があります。
熊日赤の年休取得平均は日赤全体平均の約半分程度ですから、かなり大きな開きがあります。
年休5日取得義務化について
労働基準法では、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、一定の要件を満たす労働者に対し、毎年一定日数の年次有給休暇を与えることを規定しています。
労働基準法が改正され、2019(平成31)年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。
♥使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければなりません。
♥年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。
有給休暇取得日の指定義務化に対する企業側の対応として、「個別指定方式」と「計画年休制度の導入」の2つの選択肢があります。
◇ 個別指定方式は、従業員ごとに消化日数が5日以上になっているかをチェックし、5日未満になってしまいそうな従業員について、会社が有給休暇取得日を指定する方法です。例えば、就業規則で、「基準日から1年間の期間が終わる1ヵ月前までに有給休暇が5日未満の従業員について会社が有給休暇を指定する」ことを定めて、実行していくことが考えられます。
有給休暇取得日の指定義務化に対する企業側の対応のひとつとして「計画年休制度の導入」の選択肢があります。
◇計画年休制度とは、会社が従業員代表との労使協定により、各従業員の有給休暇をあらかじめ日にちを決めることができる制度です。ただし最低5日は自由に取得できる年休としなければなりません。法改正の前から存在する制度で、労働基準法39条6項に定められています。
(1) 計画年休制度では、以下のようなさまざまなパターンの制度設計が可能です。
① 全社一斉に特定の日を有給休暇とするパターン・・・製造部門など、操業をストップさせて全従業員を休ませることのできる事業場などで活用
② 部署ごとに有給休暇をとる日を分けるパターン・・・流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業、事業場で活用
③ 有給休暇をとる日を1人ずつ決めていくパターン・・・夏季、年末年始、GWのほか、誕生日や結婚記念日など従業員の個人的な記念日を優先的に充てるケースも多いようです。
(2) 企業にとっては「個別の従業員ごとの管理が必要なくなる」ことで取り入れている所も少なくありません。今までは「年休が取れていない人がいるようだ」程度の認識でも許されましたが、これからは法律で使用者が罰せられる(6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金)ことから管理の徹底が求められます。また計画年休を実施する際は労使協定が必要です。協定で決められた有給休暇取得日は会社側の都合で変更することはできません。
(3) 従来から交替制職場の勤務表に、希望していない年休が「この日年休にしておいたから」と勝手に指定されるケースが見受けられますが、厳密にいえば、これも計画年休の協定がなければ違法行為となります。
長くなるので本日はここまで 次回に続く・・・

これは先進諸国の中でも日本において極端に年休取得率が低いことに起因し改善の必要性が迫られた背景もあります。
しかし目標数値を掲げたものの実態として年休取得率がほとんど伸びていないことから、実質的な数値を上げるために来年4月1日から企業に対し雇用する職員に年休5日取得を義務化することが決定しました。
ちなみに日本赤十字社の場合、2017年(H29年)全体平均は8.1日です。
厚労省の「平成 29 年就労条件総合調査」(平29.12.29)によると、平成 28 年(又は平成 27 会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数によると、企業規模1000人以上の職場は平均55.3%の取得率です。
この調査の数値を日本赤十字社に当てはめると21日×55.3%=平均11.6日となります。なので取得率は日本赤十字社全体平均値38.5%(平均8.1日)は同規模企業と比べても3日程度低い現状にあります。
この政府の掲げる年休取得70%を日赤職場で実現するには15日(14.7日)/年取得する必要があります。
熊日赤の年休取得平均は日赤全体平均の約半分程度ですから、かなり大きな開きがあります。
年休5日取得義務化について
労働基準法では、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、一定の要件を満たす労働者に対し、毎年一定日数の年次有給休暇を与えることを規定しています。
労働基準法が改正され、2019(平成31)年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。
♥使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければなりません。
♥年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。
有給休暇取得日の指定義務化に対する企業側の対応として、「個別指定方式」と「計画年休制度の導入」の2つの選択肢があります。
◇ 個別指定方式は、従業員ごとに消化日数が5日以上になっているかをチェックし、5日未満になってしまいそうな従業員について、会社が有給休暇取得日を指定する方法です。例えば、就業規則で、「基準日から1年間の期間が終わる1ヵ月前までに有給休暇が5日未満の従業員について会社が有給休暇を指定する」ことを定めて、実行していくことが考えられます。
有給休暇取得日の指定義務化に対する企業側の対応のひとつとして「計画年休制度の導入」の選択肢があります。
◇計画年休制度とは、会社が従業員代表との労使協定により、各従業員の有給休暇をあらかじめ日にちを決めることができる制度です。ただし最低5日は自由に取得できる年休としなければなりません。法改正の前から存在する制度で、労働基準法39条6項に定められています。
(1) 計画年休制度では、以下のようなさまざまなパターンの制度設計が可能です。
① 全社一斉に特定の日を有給休暇とするパターン・・・製造部門など、操業をストップさせて全従業員を休ませることのできる事業場などで活用
② 部署ごとに有給休暇をとる日を分けるパターン・・・流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業、事業場で活用
③ 有給休暇をとる日を1人ずつ決めていくパターン・・・夏季、年末年始、GWのほか、誕生日や結婚記念日など従業員の個人的な記念日を優先的に充てるケースも多いようです。
(2) 企業にとっては「個別の従業員ごとの管理が必要なくなる」ことで取り入れている所も少なくありません。今までは「年休が取れていない人がいるようだ」程度の認識でも許されましたが、これからは法律で使用者が罰せられる(6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金)ことから管理の徹底が求められます。また計画年休を実施する際は労使協定が必要です。協定で決められた有給休暇取得日は会社側の都合で変更することはできません。
(3) 従来から交替制職場の勤務表に、希望していない年休が「この日年休にしておいたから」と勝手に指定されるケースが見受けられますが、厳密にいえば、これも計画年休の協定がなければ違法行為となります。
長くなるので本日はここまで 次回に続く・・・

2018年11月23日
来年4月より罰則付き(会社側に対し)で時間外労働の上限が設けられます。
2019年4月より、36協定で定める時間外労働に、罰則付きの上限が設けられます。
36協定とは
労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内(日赤の場合は1日7時間45分)とされています。
これを「法定労働時間」といいます。本来、労基法では会社が職員(労働者)を法定労働時間外に働かせることはしてはいけません。ただし一時的・臨時的な場合に限り時間外労働をさせることが出来ます。
さらにこの法定労働時間を超えて職員(労働者)に時間外労働をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定の締結、所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限」などを決めなければなりません。
厚生労働省では、日本社会全体でまだまだ時間外労働が蔓延、長時間労働が慢性化している実態を受け、36協定で定める時間外労働及び休日労働について新たに指針を策定しました。
時間外労働の上限規制が設けられる
今回の指針で、36協定で定める時間外労働時間に、罰則付きの上限が設けられました!
2018年6月の労働基準法改正で、2019年4月より36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限が設けられることとなりました。
時間外労働の上限「限度時間」は、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
※臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。また、月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。
厚生労働省の36協定に関する新たな指針で次の留意点が示されています。
① 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。(指針第2条)
② 使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負います。また、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意する必要があります。(指針第3条)
36協定の範囲内で労働させた場合であっても、労働契約法第5条の安全配慮義務を負うことに留意しなければなりません。
「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(H13年12月12日付け基発第1063号厚生労働省労働基準局長通達)において、1週間当たり40時間を超える労働時間が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まるとされていること。
さらに、1週間当たり40時間を超える労働時間が月100時間又は2~6か月平均で80時間を超える場合には、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いとされていることに留意しなければなりません。※過労死ライン
③ 時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にしてください。(指針第4条)
④ 臨時的な特別の事情がなければ、限度時間(月45時間・年360時間)を超えることはできません。
限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、できる限り具体的に定めなければなりません。この場合にも、時間外労働は、限度時間にできる限り近づけるように努めてください。(指針第5条)
限度時間を超えて労働させることができる場合を定めるに当たっては、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に定めなければなりません。
「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものは認められません。
時間外労働は原則として限度時間を超えないものとされていることに十分留意し、
(1)1か月の時間外労働及び休日労働の時間、
(2)1年の時間外労働時間、を限度時間にできる限り近づけるように努めなければなりません。
限度時間を超える時間外労働については、25%を超える割増賃金率とするように努めなければなりません。
⑤ 1か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間(※)を超えないように努めてください。(指針第6条)
(※)1週間:15時間、2週間:27時間、4週間:43時間
⑥ 休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めてください。(指針第7条)
⑦ 限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保してください。(指針第8条)
限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保するための措置について、次の中から協定することが望ましいことに留意しなければなりません。
①医師による面接指導
②深夜業の回数制限
③終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
④代償休日・特別な休暇の付与
⑤健康診断
⑥連続休暇の取得
⑦心とからだの相談窓口の設置
⑧配置転換
⑨産業医等による助言・指導や保健指導

36協定とは
労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内(日赤の場合は1日7時間45分)とされています。
これを「法定労働時間」といいます。本来、労基法では会社が職員(労働者)を法定労働時間外に働かせることはしてはいけません。ただし一時的・臨時的な場合に限り時間外労働をさせることが出来ます。
さらにこの法定労働時間を超えて職員(労働者)に時間外労働をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定の締結、所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限」などを決めなければなりません。
厚生労働省では、日本社会全体でまだまだ時間外労働が蔓延、長時間労働が慢性化している実態を受け、36協定で定める時間外労働及び休日労働について新たに指針を策定しました。
時間外労働の上限規制が設けられる
今回の指針で、36協定で定める時間外労働時間に、罰則付きの上限が設けられました!
2018年6月の労働基準法改正で、2019年4月より36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限が設けられることとなりました。
時間外労働の上限「限度時間」は、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
※臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。また、月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。
厚生労働省の36協定に関する新たな指針で次の留意点が示されています。
① 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。(指針第2条)
② 使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負います。また、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意する必要があります。(指針第3条)
36協定の範囲内で労働させた場合であっても、労働契約法第5条の安全配慮義務を負うことに留意しなければなりません。
「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(H13年12月12日付け基発第1063号厚生労働省労働基準局長通達)において、1週間当たり40時間を超える労働時間が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まるとされていること。
さらに、1週間当たり40時間を超える労働時間が月100時間又は2~6か月平均で80時間を超える場合には、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いとされていることに留意しなければなりません。※過労死ライン
③ 時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にしてください。(指針第4条)
④ 臨時的な特別の事情がなければ、限度時間(月45時間・年360時間)を超えることはできません。
限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、できる限り具体的に定めなければなりません。この場合にも、時間外労働は、限度時間にできる限り近づけるように努めてください。(指針第5条)
限度時間を超えて労働させることができる場合を定めるに当たっては、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に定めなければなりません。
「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものは認められません。
時間外労働は原則として限度時間を超えないものとされていることに十分留意し、
(1)1か月の時間外労働及び休日労働の時間、
(2)1年の時間外労働時間、を限度時間にできる限り近づけるように努めなければなりません。
限度時間を超える時間外労働については、25%を超える割増賃金率とするように努めなければなりません。
⑤ 1か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間(※)を超えないように努めてください。(指針第6条)
(※)1週間:15時間、2週間:27時間、4週間:43時間
⑥ 休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めてください。(指針第7条)
⑦ 限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保してください。(指針第8条)
限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保するための措置について、次の中から協定することが望ましいことに留意しなければなりません。
①医師による面接指導
②深夜業の回数制限
③終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
④代償休日・特別な休暇の付与
⑤健康診断
⑥連続休暇の取得
⑦心とからだの相談窓口の設置
⑧配置転換
⑨産業医等による助言・指導や保健指導

2017年02月02日
1月20日付けで厚労省はサービス残業根絶のための新通達
1月20日付けで厚労省はサービス残業根絶のための新通達を出しました。
これは厚労省労働局長が各都道府県労働局長にあてて、使用者によってごまかされがちな労働時間や電通過労自死事件などで問題となった残業時間の自己申告制などの対応について明文化しています。
新設した『労働時間の考え方』の項目には
労働者が使用者の指揮命令下にあれば明示的な指示がなくても労働時間にあたるとしています。
●労働時間として認められるもの(具体例)
着替えなどの準備行為
清掃などの後始末
指示があればすぐに業務に入る必要がある待機時間(いわゆる手待ち時間)
参加義務のある研修や学習など
労働者に労働時間を自己申告させる際に、実際の労働時間より短く報告させる過少申告が問題になっている『自己申告制』について
●使用者が講ずべき措置として
職場の入場記録や、パソコン使用時間の記録などと自己申告時間のかい離をもとに実態調査し、補正することを明記。
『自主的な研修』なども、実際には使用者の指揮命令下にあれば労働時間として扱う。
この新通達の趣旨には、『使用者は、ガイドラインを順守すべきものである』と記載。
順守指導において悪質事案では『司法処分を含めて厳正に対処』するとしています。
これは厚労省労働局長が各都道府県労働局長にあてて、使用者によってごまかされがちな労働時間や電通過労自死事件などで問題となった残業時間の自己申告制などの対応について明文化しています。
新設した『労働時間の考え方』の項目には
労働者が使用者の指揮命令下にあれば明示的な指示がなくても労働時間にあたるとしています。
●労働時間として認められるもの(具体例)
着替えなどの準備行為
清掃などの後始末
指示があればすぐに業務に入る必要がある待機時間(いわゆる手待ち時間)
参加義務のある研修や学習など
労働者に労働時間を自己申告させる際に、実際の労働時間より短く報告させる過少申告が問題になっている『自己申告制』について
●使用者が講ずべき措置として
職場の入場記録や、パソコン使用時間の記録などと自己申告時間のかい離をもとに実態調査し、補正することを明記。
『自主的な研修』なども、実際には使用者の指揮命令下にあれば労働時間として扱う。
この新通達の趣旨には、『使用者は、ガイドラインを順守すべきものである』と記載。
順守指導において悪質事案では『司法処分を含めて厳正に対処』するとしています。
2017年01月24日
「過労死ゼロ」緊急対策=(厚労省2016.12.26)
電通の過労死事件を受けて、昨年末、厚生労働省は【過労死等ゼロ】緊急対策を打ち出しました。
今年2017年1月1日からスタートです。
その中には企業に対し、新たなガイドラインを定め、労働時間の適正把握を徹底することや、違法な長時間労働等を複数の事業場で行う等の企業に対して全社的な是正指導を行うこと。労働行政がパワハラ対策の必要性、予防・解決のために必要な取組なども含め指導を行うこと等が盛り込まれています。
新ガイドラインによる労働時間の適正把握の徹底に関し厚労省は新たな取り組みとして
下記のことが新たに追加されました。
○使用者向けに、労働時間の適正把握のためのガイドラインを新たに定める。
○内容として、
①労働者の「実労働時間(※残業を行った時間を含む全ての労働時間)」と「自己申告した労働時間」に乖離がある場合、使用者は実態調査を行うこと
②「使用者の明示または黙示の指示により自己啓発等の学習や研修受講をしていた時間」は労働時間として取り扱わなければならないこと等を明確化する(2017年1月1日より実施)
この②については
日赤職場でも常態化している
○○委員会、○○学習会、研集会等、職場で行われ、いままでは「自己研鑽」として上司から時間外労働なのかが曖昧にされ、時間外勤務命令簿に書きづらかったものが「労働時間」として取り扱わなければならない。と明確に打ち出された画期的な取組です。
『使用者の明示』というのは「上司(課長・師長クラス)が業務命令として発した場合を指しますが、『黙示の指示』とは「上司がその会議等の必要性を認識していたり、執拗に参加を促したり、出席を暗に強制している場合も”業務命令があった”と見なされます。
「出てもらわなければ困る」
「あなただけが○○学習会に出ていないわよ」
「まだ受けてないの?」
「自己研鑽の為」
と言って暗に出席を強制させられる就業時間外の委員会、学習会、研集会等は労働時間となると言っていいでしょう。
逆に「出席しなくても良い、有志の学習会」「チラシなどで宣伝しただけの研集会」「受講してもしなくても個人の評価や日常業務に影響が無いもの」は労働時間にはあたらないといえます。
ここまで読んで、ふと気づきませんか?日赤職場で看護部を中心にこの「自己研鑽」で出席させられる業務が多かったと。
それはほぼ全て時間外労働として認められ、病院は時間外手当を支払わなければならないものです。
これは、もう2度と電通のような過労死、過労自死をうまない為の国の施策であり、組合もこの事に大いに賛同し推進していきます。
職員の皆さん。是非、正確な時間外請求を行い、もし時間外申請が勝手に削られている、申請前に上司に削除を迫られた、朝礼で時間外申請の抑制を言われているといった事があれば、労働組合にご連絡下さい。
今年2017年1月1日からスタートです。
その中には企業に対し、新たなガイドラインを定め、労働時間の適正把握を徹底することや、違法な長時間労働等を複数の事業場で行う等の企業に対して全社的な是正指導を行うこと。労働行政がパワハラ対策の必要性、予防・解決のために必要な取組なども含め指導を行うこと等が盛り込まれています。
新ガイドラインによる労働時間の適正把握の徹底に関し厚労省は新たな取り組みとして
下記のことが新たに追加されました。
○使用者向けに、労働時間の適正把握のためのガイドラインを新たに定める。
○内容として、
①労働者の「実労働時間(※残業を行った時間を含む全ての労働時間)」と「自己申告した労働時間」に乖離がある場合、使用者は実態調査を行うこと
②「使用者の明示または黙示の指示により自己啓発等の学習や研修受講をしていた時間」は労働時間として取り扱わなければならないこと等を明確化する(2017年1月1日より実施)
この②については
日赤職場でも常態化している
○○委員会、○○学習会、研集会等、職場で行われ、いままでは「自己研鑽」として上司から時間外労働なのかが曖昧にされ、時間外勤務命令簿に書きづらかったものが「労働時間」として取り扱わなければならない。と明確に打ち出された画期的な取組です。
『使用者の明示』というのは「上司(課長・師長クラス)が業務命令として発した場合を指しますが、『黙示の指示』とは「上司がその会議等の必要性を認識していたり、執拗に参加を促したり、出席を暗に強制している場合も”業務命令があった”と見なされます。
「出てもらわなければ困る」
「あなただけが○○学習会に出ていないわよ」
「まだ受けてないの?」
「自己研鑽の為」
と言って暗に出席を強制させられる就業時間外の委員会、学習会、研集会等は労働時間となると言っていいでしょう。
逆に「出席しなくても良い、有志の学習会」「チラシなどで宣伝しただけの研集会」「受講してもしなくても個人の評価や日常業務に影響が無いもの」は労働時間にはあたらないといえます。
ここまで読んで、ふと気づきませんか?日赤職場で看護部を中心にこの「自己研鑽」で出席させられる業務が多かったと。
それはほぼ全て時間外労働として認められ、病院は時間外手当を支払わなければならないものです。
これは、もう2度と電通のような過労死、過労自死をうまない為の国の施策であり、組合もこの事に大いに賛同し推進していきます。
職員の皆さん。是非、正確な時間外請求を行い、もし時間外申請が勝手に削られている、申請前に上司に削除を迫られた、朝礼で時間外申請の抑制を言われているといった事があれば、労働組合にご連絡下さい。
2017年01月10日
長時間労働が蔓延する現場で…労働行政の今。
昨年は電通の若い女性社員の過労自死の労災認定を受け、東京労働局などは、労務管理を担当する幹部も違法な長時間労働が常態化していた職場の実情を把握していたとし、労働基準法違反の疑いで書類送検しました。
それを受け、社会的責任を取る形で社長が辞任する事態なっています。
厚生労働省は昨年12月26日、違法な長時間労働を行った企業に対する企業名公表制度を現行の月100時間超から、月80時間超に引き下げることを「長時間労働削減推進本部」で決定しました。
また、過労死等・過労自殺等で労災の支給が決定した場合も対象となります。
複数の事業場で違法な長時間労働が認められた場合には全社的な立入調査を行うことが盛り込まれています。
80時間超への引き下げは、2017年(平成29年)より実施となります。
2事業場で上記労災支給が行われた場合には、企業本社への指導を実施し、是正されない場合に公表するとされています。
月100時間超と過労死・過労自殺が2事業場に認められた場合にも企業名公表となります。
日本は「働きすぎ社会」と言われ、「過労死」という言葉も生まれました。
外国語には「過労死」を訳する言葉はなく、働きすぎて命を落とすということ自体が
日本独特のものであるといえます。
こういった風土は過去のものとしなければ同じ悲劇を繰り返すことになりかねません。
それを受け、社会的責任を取る形で社長が辞任する事態なっています。
厚生労働省は昨年12月26日、違法な長時間労働を行った企業に対する企業名公表制度を現行の月100時間超から、月80時間超に引き下げることを「長時間労働削減推進本部」で決定しました。
また、過労死等・過労自殺等で労災の支給が決定した場合も対象となります。
複数の事業場で違法な長時間労働が認められた場合には全社的な立入調査を行うことが盛り込まれています。
80時間超への引き下げは、2017年(平成29年)より実施となります。
2事業場で上記労災支給が行われた場合には、企業本社への指導を実施し、是正されない場合に公表するとされています。
月100時間超と過労死・過労自殺が2事業場に認められた場合にも企業名公表となります。
日本は「働きすぎ社会」と言われ、「過労死」という言葉も生まれました。
外国語には「過労死」を訳する言葉はなく、働きすぎて命を落とすということ自体が
日本独特のものであるといえます。
こういった風土は過去のものとしなければ同じ悲劇を繰り返すことになりかねません。
2016年09月13日
厚生年金保険・健康保険の「改正」 短時間労働者の適用拡大はじまる !
2016年10月1日から短時間労働者(日赤職員でいう嘱託・臨時・パート職員のうち一定の条件を満たした労働者)に対して、新たに厚生年金保険・健康保険への加入が適用拡大されます。
いままでは、一般的に週30時間以上働く労働者が厚生年金保険・健康保険の加入対象でしたが、国の制度「改正」で10月1日からは週20時間以上働く労働者にも対象が広がります。また、いわゆる年収130万円の壁も106万円に引き下がります。
この「改正」により、勤務先の健保に入れずに国民健康保険に入っていた人は、保険料が引き下がるなどの改善となりますが、配偶者等の扶養家族(第3号被保険者)となっていた人は、これからは自分で保険料を支払うことになり負担が増えるものです。しかし負担が増えることで年金等におけるメリットも発生しますので、よく考えて個々人が対応する必要があります。
日赤の全事業所が対象
〇10月1日から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険・健康保険の適用対象となります。
特定適用事業所とは
〇日赤は、一つの法人であり同一事業主として特定適用事業所の基準を満たすので、全国の日赤施設はもとより熊本日赤でも適用拡大の対象となります。
短時間労働者とは
〇勤務時間・勤務日数が常時雇用者(フルタイム労働者)の4分の3未満で、以下の5要件①~⑤の全てに該当する職員が適用拡大の対象者となります。
※ 4分の3以上の人は既に厚生年金保険・健康保険の適用となっています。
※ 現在、短時間(臨時・嘱託・パート)で働く職員、第1号被保険者(自身で国民健康保険に加入している方)、第3号被保険者(配偶者の健康保険に加入している方:主婦パート等)が適用拡大の対象になる可能性があります。
①週の所定労働時間が20時間以上であること(※雇用保険に入っている労働者)
②雇用期間が継続して1年以上見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上であること
④学生でないこと
⑤特定適用事業所に勤めていること
?常時雇用者(フルタイム労働者)の4分の3未満ってなに?
例えば、日赤の正規職員は週38時間45分ですが、週5日勤務(5×4週=月20日勤務※厚労省のQ&Aによる計算)の場合には、4分の3は週29時間04分以上及び月15日勤務以上となります。
(想定ケース)1週の所定労働日数が5日の非正規職員(育児短時間勤務は除く)で
(1) 1日の所定労働時間が6時間なら・・週30時間、月20日で4分の3以上
※既に適用となっている
(2) 1日の所定労働時間が5時間なら・・週25時間、月20日で4分の3以下
※20時間以上で拡大対象、ただし時給880円未満の場合は対象外
(3) 1日の所定労働時間が4時間なら・・週20時間、月20日で4分の3以下
※20時間以上で拡大対象、ただし時給1100円未満の場合は対象外
(4) 1日の所定労働時間が3時間なら・・週15時間、月20日で4分の3以下
※20時間以下で対象外
?賃金の月額が8.8万円以上であることの賃金って?
賃金の月額が、88,000円以上(年収106万円)であることとは、雇用契約書に記載されている週給、日給、時間給を月額に換算したもの(基本給)に、各諸手当等を含めた所定内賃金の額が88,000円以上である場合となります。但し、次の①~④の賃金は除かれます。
①臨時に支払われる賃金(出産お祝い金など※厚労省Q&Aの例示)
②1月を超える期間ごとに払われる賃金(賞与などの一時金)
③時間外労働に支払われる賃金、休日労働及び、深夜労働に対して支払われる賃金
(割増賃金)
④最低賃金において算入しないことを定める賃金(通勤手当、家族手当、精皆勤手当)
保険料・掛金の計算 (2016年10月時点の料率にて計算)
健康保険の掛け金の計算は次のとおりです。
(標準報酬月額)×(日赤健保掛金率91.60‰×2分の1)=健康保険の掛け金
例:月額90,000円の賃金の場合で日赤健保加入の場合
(標準報酬月額88,000)×(91.60‰×2分の1)=4,030円
また、健康保険の被保険者に該当する40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となるため、健康保険料と合わせて、介護保険料の被保険者負担分を賃金から控除されますので注意が必要です。
介護保険料の掛金(労働者負担分)
(標準報酬月額)×(日赤健保介護保険料率11.40‰)=介護保険料
例:月額90,000円の賃金の場合で日赤健保加入の場合
(標準報酬月額88,000)×(11.40‰×2分の1)=502円
厚生年金保険の掛け金(労働者負担分)は次のとおりです。
(標準報酬月額)×(日赤年金基金保険料18.182‰×2分の1)=厚生年金保険掛け金
例:月額90,000円の賃金の場合
(標準報酬月額88,000)×(18.182‰×2分の1)=8,000円
※社会保険料の掛金を負担することで収入減となります。また健康保険における夫の扶養家族から外れることで、会社によっては夫の扶養手当が無くなることも予想されます。以下は例えば…
(1) 月額90,000円の39歳以下Aさんの場合の手取額
90,000-[(健康保険組合労働者負担分4,030円)+厚生年金保険料8,000円]=77,970円
(2) 月額90,000円の40歳以上Bさんの場合の手取額
90,000-[(健康保険組合労働者負担分4,532円)+厚生年金保険料8,000円]=77,468円
健康保険・厚生年金のメリット
健康保険に本人が加入するメリットは次のことが挙げられます。
(1) 健康保険料の半額を会社が負担してくれるので、個人で全額負担していた場合に比べて負担額が軽くなる。
(2) 傷病手当金・出産手当金を受給することができる。
①私傷病で労務不能となった場合、月給の約67%が最大1年6か月間、傷病手当金として受給でき、病気の時も安心です。健康保険の被扶養者は傷病手当金を受給することが出来ませんので大きなメリットとなります。
②出産のため労務に従事しなかった場合、産前(42日間)産後(56日間)合計98日間、月給の約67%を出産手当金として受給することが出来ます。健康保険の被扶養者は出産手当金を受給することが出来ませんので大きなメリットとなります。
厚生年金に本人が加入するメリットは次のことが挙げられます。
(1) 年金保険料の半額を会社が負担してくれるので、国民年金に個人で全額負担していた場合に比べて負担額が軽くなる。
(2) 老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金を受給できる。
①国民年金だけ加入していると障害基礎年金1級または2級しか受給出来ませんが、障害厚生年金を受給できるようになると、1級の場合、障害基礎年金1級+障害厚生年金1級が、2級の場合、障害基礎年金2級+障害厚生年金2級が、3級の場合、障害厚生年金3級が、その他障害手当金が受給出来ます。
②遺族厚生年金を受給できるようになれば、国民年金より受給要件が緩和されていますので、遺族の方が幅広く受給出来ます。
③老齢厚生年金を受給できるようになると加入期間、その間の報酬額にもよりますが、国民年金だけ加入していた時より、老後に多くの年金を受給出来ます。
※現在の国民年金から日赤年金基金に加入する事によって将来貰える年金額
例えば、月収90,000円のAさんの場合
ex)月収90,000円 保険料 増える年金額(目安)
40年間加入 月額8,000円/年額96,000 月額19,300円/年額231,500×終身
20年間加入 月額8,000円/年額96,000 月額 9,700円/年額115,800×終身
1年間加入 月額8,000円/年額96,000 月額 500円/年額 5,800×終身
病院側が、掛金を半分負担する健康保険や厚生年金に加入することは改善だと思いますが、それにより掛金の本人負担や税金関係で家計の収入が減るのは避けられない状況であるといえます。
個々の家庭環境の違いにより対応も変わると思うので、対象となる方は今後の働き方を考える上でも参考にしてくださいね。
いままでは、一般的に週30時間以上働く労働者が厚生年金保険・健康保険の加入対象でしたが、国の制度「改正」で10月1日からは週20時間以上働く労働者にも対象が広がります。また、いわゆる年収130万円の壁も106万円に引き下がります。
この「改正」により、勤務先の健保に入れずに国民健康保険に入っていた人は、保険料が引き下がるなどの改善となりますが、配偶者等の扶養家族(第3号被保険者)となっていた人は、これからは自分で保険料を支払うことになり負担が増えるものです。しかし負担が増えることで年金等におけるメリットも発生しますので、よく考えて個々人が対応する必要があります。
日赤の全事業所が対象
〇10月1日から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険・健康保険の適用対象となります。
特定適用事業所とは
〇日赤は、一つの法人であり同一事業主として特定適用事業所の基準を満たすので、全国の日赤施設はもとより熊本日赤でも適用拡大の対象となります。
短時間労働者とは
〇勤務時間・勤務日数が常時雇用者(フルタイム労働者)の4分の3未満で、以下の5要件①~⑤の全てに該当する職員が適用拡大の対象者となります。
※ 4分の3以上の人は既に厚生年金保険・健康保険の適用となっています。
※ 現在、短時間(臨時・嘱託・パート)で働く職員、第1号被保険者(自身で国民健康保険に加入している方)、第3号被保険者(配偶者の健康保険に加入している方:主婦パート等)が適用拡大の対象になる可能性があります。
①週の所定労働時間が20時間以上であること(※雇用保険に入っている労働者)
②雇用期間が継続して1年以上見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上であること
④学生でないこと
⑤特定適用事業所に勤めていること
?常時雇用者(フルタイム労働者)の4分の3未満ってなに?
例えば、日赤の正規職員は週38時間45分ですが、週5日勤務(5×4週=月20日勤務※厚労省のQ&Aによる計算)の場合には、4分の3は週29時間04分以上及び月15日勤務以上となります。
(想定ケース)1週の所定労働日数が5日の非正規職員(育児短時間勤務は除く)で
(1) 1日の所定労働時間が6時間なら・・週30時間、月20日で4分の3以上
※既に適用となっている
(2) 1日の所定労働時間が5時間なら・・週25時間、月20日で4分の3以下
※20時間以上で拡大対象、ただし時給880円未満の場合は対象外
(3) 1日の所定労働時間が4時間なら・・週20時間、月20日で4分の3以下
※20時間以上で拡大対象、ただし時給1100円未満の場合は対象外
(4) 1日の所定労働時間が3時間なら・・週15時間、月20日で4分の3以下
※20時間以下で対象外
?賃金の月額が8.8万円以上であることの賃金って?
賃金の月額が、88,000円以上(年収106万円)であることとは、雇用契約書に記載されている週給、日給、時間給を月額に換算したもの(基本給)に、各諸手当等を含めた所定内賃金の額が88,000円以上である場合となります。但し、次の①~④の賃金は除かれます。
①臨時に支払われる賃金(出産お祝い金など※厚労省Q&Aの例示)
②1月を超える期間ごとに払われる賃金(賞与などの一時金)
③時間外労働に支払われる賃金、休日労働及び、深夜労働に対して支払われる賃金
(割増賃金)
④最低賃金において算入しないことを定める賃金(通勤手当、家族手当、精皆勤手当)
保険料・掛金の計算 (2016年10月時点の料率にて計算)
健康保険の掛け金の計算は次のとおりです。
(標準報酬月額)×(日赤健保掛金率91.60‰×2分の1)=健康保険の掛け金
例:月額90,000円の賃金の場合で日赤健保加入の場合
(標準報酬月額88,000)×(91.60‰×2分の1)=4,030円
また、健康保険の被保険者に該当する40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となるため、健康保険料と合わせて、介護保険料の被保険者負担分を賃金から控除されますので注意が必要です。
介護保険料の掛金(労働者負担分)
(標準報酬月額)×(日赤健保介護保険料率11.40‰)=介護保険料
例:月額90,000円の賃金の場合で日赤健保加入の場合
(標準報酬月額88,000)×(11.40‰×2分の1)=502円
厚生年金保険の掛け金(労働者負担分)は次のとおりです。
(標準報酬月額)×(日赤年金基金保険料18.182‰×2分の1)=厚生年金保険掛け金
例:月額90,000円の賃金の場合
(標準報酬月額88,000)×(18.182‰×2分の1)=8,000円
※社会保険料の掛金を負担することで収入減となります。また健康保険における夫の扶養家族から外れることで、会社によっては夫の扶養手当が無くなることも予想されます。以下は例えば…
(1) 月額90,000円の39歳以下Aさんの場合の手取額
90,000-[(健康保険組合労働者負担分4,030円)+厚生年金保険料8,000円]=77,970円
(2) 月額90,000円の40歳以上Bさんの場合の手取額
90,000-[(健康保険組合労働者負担分4,532円)+厚生年金保険料8,000円]=77,468円
健康保険・厚生年金のメリット
健康保険に本人が加入するメリットは次のことが挙げられます。
(1) 健康保険料の半額を会社が負担してくれるので、個人で全額負担していた場合に比べて負担額が軽くなる。
(2) 傷病手当金・出産手当金を受給することができる。
①私傷病で労務不能となった場合、月給の約67%が最大1年6か月間、傷病手当金として受給でき、病気の時も安心です。健康保険の被扶養者は傷病手当金を受給することが出来ませんので大きなメリットとなります。
②出産のため労務に従事しなかった場合、産前(42日間)産後(56日間)合計98日間、月給の約67%を出産手当金として受給することが出来ます。健康保険の被扶養者は出産手当金を受給することが出来ませんので大きなメリットとなります。
厚生年金に本人が加入するメリットは次のことが挙げられます。
(1) 年金保険料の半額を会社が負担してくれるので、国民年金に個人で全額負担していた場合に比べて負担額が軽くなる。
(2) 老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金を受給できる。
①国民年金だけ加入していると障害基礎年金1級または2級しか受給出来ませんが、障害厚生年金を受給できるようになると、1級の場合、障害基礎年金1級+障害厚生年金1級が、2級の場合、障害基礎年金2級+障害厚生年金2級が、3級の場合、障害厚生年金3級が、その他障害手当金が受給出来ます。
②遺族厚生年金を受給できるようになれば、国民年金より受給要件が緩和されていますので、遺族の方が幅広く受給出来ます。
③老齢厚生年金を受給できるようになると加入期間、その間の報酬額にもよりますが、国民年金だけ加入していた時より、老後に多くの年金を受給出来ます。
※現在の国民年金から日赤年金基金に加入する事によって将来貰える年金額
例えば、月収90,000円のAさんの場合
ex)月収90,000円 保険料 増える年金額(目安)
40年間加入 月額8,000円/年額96,000 月額19,300円/年額231,500×終身
20年間加入 月額8,000円/年額96,000 月額 9,700円/年額115,800×終身
1年間加入 月額8,000円/年額96,000 月額 500円/年額 5,800×終身
病院側が、掛金を半分負担する健康保険や厚生年金に加入することは改善だと思いますが、それにより掛金の本人負担や税金関係で家計の収入が減るのは避けられない状況であるといえます。
個々の家庭環境の違いにより対応も変わると思うので、対象となる方は今後の働き方を考える上でも参考にしてくださいね。











