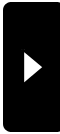2023年08月01日
<重要なお報せ>全日赤熊本結成しました!!!
皆さん大変にご無沙汰しております。
まず、このブログに足を運んで下さっている皆さま、大変長らく更新せずにいましたことを謝りたいと思います

更新しない間にあった事を簡単にご報告します。
(交渉議題は年休取得促進や時間外手当申請に関すること、非正規職員の処遇改善、2023年4月の新賃金移行に関して、ハラスメント被害など等です)
他に、ブログを観て下さった方々からご相談も頂いています。
交渉や折衝の結果、権利獲得や病院が職員の為に約束をした事、夏期一時金を昨年より0.1ヵ月増を回答したとかありましたが、ごめんないさい。
 書き切れないため、追々ご報告出来たら良いなと思っています
書き切れないため、追々ご報告出来たら良いなと思っています
このように、いろいろな活動をしていたところ昨年より、組合加入者が増え、より職場改善を進めるため、今年5月下旬に熊本日赤病院内に正式に熊本赤十字病院労働組合を結成する運びとなりました





写真は6月4日に結成レセプションをしたものです。
(組合名)熊本赤十字病院労働組合(通称:全日赤熊本)
(場所)熊本赤十字病院内
(連絡先
 ) zkrchp@gmail.com
) zkrchp@gmail.com(院内窓口)臨床工学部組合担当者
(臨床工学部に来所頂き、スタッフに組合の担当者さんをお願いしますとお声かけ下さい)
職員の皆さんには、是非組合加入をして、ご一緒に職場をよくする活動に参加して欲しいです



『加入はちょっと...けど話は聞いてみたいor働いていて疑問に思う労働条件の事を聞いてみたい』方はいつでもお気軽に院内窓口までご訪問下さい

直接訪問を躊躇される方は匿名でメールをお送り頂いて構いません

お待ちしています

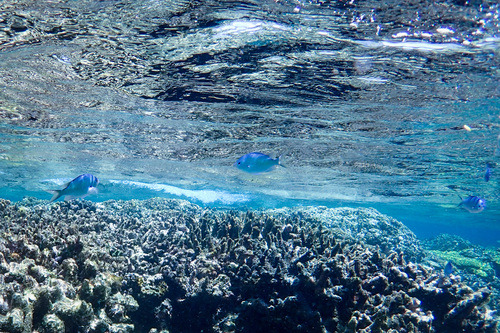
2021年05月28日
新しい「妊娠・出産・子育ての手引き(2021年度版)」パンフレットが来ました。
皆さんお疲れ様です。
私たちの職場は女性が多いのですが、日赤には
日赤職員が妊娠・出産・子育てに直面したときに、子供がいても働き続けられる様々な制度があります。
上部団体である全日赤が日赤本社と交渉し、制度自体の改善を勝ち取っていて、
ここ数年は育介法の改正もあり、1年毎に制度更新がされています。
制度が複雑で多岐に渡るため、職場でも職場長が勘違いし誤った制度や古い知識をスタッフに指南してしまうこともあるので
まずご自身で正確な制度の知識を得ることが大事です。
そこで、上部団体である全日赤が作成した、大変に活用できる日赤職員のための「働き続けようパパママ~妊娠・出産・子育ての手引き(2021年度版)」パンフレットが2021年最新バージョンが新たに発行されました。↓
http://www.zennisseki.or.jp/data/2021/pama2021s.pdf
ありがとう全日赤。パチパチ!
このパンフレット、女性職員だけでなく男性職員の権利や非正規労働者の制度等、かなりきめ細かく記載があります。
熊本県医労連では全日赤から一定数を取り寄せ、希望者に無料で配布しています。
欲しい方はぜひご連絡を。

私たちの職場は女性が多いのですが、日赤には
日赤職員が妊娠・出産・子育てに直面したときに、子供がいても働き続けられる様々な制度があります。
上部団体である全日赤が日赤本社と交渉し、制度自体の改善を勝ち取っていて、
ここ数年は育介法の改正もあり、1年毎に制度更新がされています。
制度が複雑で多岐に渡るため、職場でも職場長が勘違いし誤った制度や古い知識をスタッフに指南してしまうこともあるので
まずご自身で正確な制度の知識を得ることが大事です。
そこで、上部団体である全日赤が作成した、大変に活用できる日赤職員のための「働き続けようパパママ~妊娠・出産・子育ての手引き(2021年度版)」パンフレットが2021年最新バージョンが新たに発行されました。↓
http://www.zennisseki.or.jp/data/2021/pama2021s.pdf
ありがとう全日赤。パチパチ!
このパンフレット、女性職員だけでなく男性職員の権利や非正規労働者の制度等、かなりきめ細かく記載があります。
熊本県医労連では全日赤から一定数を取り寄せ、希望者に無料で配布しています。
欲しい方はぜひご連絡を。

2019年10月29日
働くパパママへ 前回の育短制度続き
前回投稿した育短制度の利用について、おまけの記事です。
少し難しいのですが、参考までに前回記事に併せてどうぞ。
~1号育短についての法律家の見解~中川勝之弁護士(東京法律事務所)
日本赤十字社育児休業規程の中の『1号育短』の場合、「1週間当たりの勤務時間が19時間30分から25時間までの範囲内となるように勤務すること」(11条1項(1)ロ)、「任命権者は、前項、第13条第1項、同条第3項の規定による申出があったときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、これを措置しなければならない。」(同条3項)、「勤務時間の短縮の措置を受けて育児短時間勤務をする職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)に係る始業及び終業の時刻、休憩時間、休日及び年次有給休暇については、次の各号に定めるところによる。
(1)始業及び終業の時刻、休憩時間及び休日は、当該育児短時間勤務職員の行った申出に基づき、所属長が措置するところによる。」(15条(1))等の規定の定めによると、「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当せず、申出を措置した場合、「1週間当たりの勤務時間が19時間30分から25時間まで」を満たし、「始業及び、終業の時刻、休憩時間及び休日」を申出すれば、それらが自動的に労働契約の内容(労働条件)になり、所属長の承認等の観念を容れる余地はないと解するべきである(形成権)。
なお、「所属長が措置するところによる」との規定の定めを根拠として所属長の裁量や当該職員との協議によって定められる等とすれば育短制度の趣旨が没却されるからそのような解釈は取り得ない。「措置」は、他の規定の定めからしても、単なる決定、履行や認めるといった意味に過ぎない。
そうすると、所属長による面談等による夜勤の依頼は、単なる任意の協力を求めるものに過ぎず、職員の任意の意志を尊重する様態で行われず、それが社会的相当性を逸脱する態様で行われた場合には違法と判断される。違法な夜勤の依頼は、育児・介護休業法が禁止する使用者による不利益な取扱いや上司等によるハラスメントにも該当する可能性がある。
また、「事業の正常な運営を妨げる場合」の要件は利用の申出自体を拒否するものであり、申出を措置した以上、各勤務についてその要件によって利用を制限することは出来ない。
職員本人が希望通り育短制度を利用する為の対策としては、勤務する日時及び曜日だけでなく、夜勤など勤務しない日時及び曜日も明確にすること、それらについては一切か、一定期間協議に応じないこと、仮に協議に応じる場合は(※労働組合の組合員の場合は)組合役員の立ち会いの上で行う事、それらを所属長に伝えること等が考えられる。

少し難しいのですが、参考までに前回記事に併せてどうぞ。
~1号育短についての法律家の見解~中川勝之弁護士(東京法律事務所)
日本赤十字社育児休業規程の中の『1号育短』の場合、「1週間当たりの勤務時間が19時間30分から25時間までの範囲内となるように勤務すること」(11条1項(1)ロ)、「任命権者は、前項、第13条第1項、同条第3項の規定による申出があったときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、これを措置しなければならない。」(同条3項)、「勤務時間の短縮の措置を受けて育児短時間勤務をする職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)に係る始業及び終業の時刻、休憩時間、休日及び年次有給休暇については、次の各号に定めるところによる。
(1)始業及び終業の時刻、休憩時間及び休日は、当該育児短時間勤務職員の行った申出に基づき、所属長が措置するところによる。」(15条(1))等の規定の定めによると、「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当せず、申出を措置した場合、「1週間当たりの勤務時間が19時間30分から25時間まで」を満たし、「始業及び、終業の時刻、休憩時間及び休日」を申出すれば、それらが自動的に労働契約の内容(労働条件)になり、所属長の承認等の観念を容れる余地はないと解するべきである(形成権)。
なお、「所属長が措置するところによる」との規定の定めを根拠として所属長の裁量や当該職員との協議によって定められる等とすれば育短制度の趣旨が没却されるからそのような解釈は取り得ない。「措置」は、他の規定の定めからしても、単なる決定、履行や認めるといった意味に過ぎない。
そうすると、所属長による面談等による夜勤の依頼は、単なる任意の協力を求めるものに過ぎず、職員の任意の意志を尊重する様態で行われず、それが社会的相当性を逸脱する態様で行われた場合には違法と判断される。違法な夜勤の依頼は、育児・介護休業法が禁止する使用者による不利益な取扱いや上司等によるハラスメントにも該当する可能性がある。
また、「事業の正常な運営を妨げる場合」の要件は利用の申出自体を拒否するものであり、申出を措置した以上、各勤務についてその要件によって利用を制限することは出来ない。
職員本人が希望通り育短制度を利用する為の対策としては、勤務する日時及び曜日だけでなく、夜勤など勤務しない日時及び曜日も明確にすること、それらについては一切か、一定期間協議に応じないこと、仮に協議に応じる場合は(※労働組合の組合員の場合は)組合役員の立ち会いの上で行う事、それらを所属長に伝えること等が考えられる。

2019年10月29日
働くパパママへ 正確な育短制度を知ろう
この数年、育児短時間勤務制度(育短制度)についての問い合わせや質問が少なからず寄せられています。本日は、よくある質問に答えます。
Q1.現在育休中の看護師です。もうすぐ職場復帰をしますが、育短制度を利用したいと思っています。
労働組合のパンフレットhttp://www.zennisseki.or.jp/data/2017/pama2017s.pdfを見ましたが育短の申請時間を自分で決めると記載してあります。
家庭の事情もあり週3日勤務(2日間7時間45分、1日間4時間)=19時間30分/週で、夜勤出来ない(※1号育短)、この勤務で申請をしたいと考えています。
最近、病院の師長さんに呼ばれ面談した際に復帰後の勤務についての話になりこの希望を伝えると、師長さんから「当院は育短制度の6時間に短縮(※3号育短)しかしていない。夜勤もして貰わないと」と一方的に言われました。師長さんの言う通りにしないといけないのでしょうか?
A1. 育児短時間制度は大きく分けて3つの時間短縮制度と4つの勤務制限措置制度があります。この内容は全国の日赤施設で全社共通です。
例)看護師の場合(※交代制勤務者以外の方の場合は制度内容に少し違いがあるので注意)
時間短縮制度(下記の『1号育短』等の名称は分かりやすくするための通称であり、制度自体は育児休業規程第11条(1)の規程です)
(1号育短)1週間あたりの勤務時間が19時間30分から25時間までの範囲の勤務
(2号育短)始業または終業を1日を通じて2時間30分を超えない範囲で30分に短縮
(3号育短)1日の労働時間を6時間に短縮
勤務制限措置
①時差出勤
②所定労働時間を超えない勤務
③時間外勤務の制限
④深夜勤務の免除※左記以外でも上記育短1号で夜勤をしない申出をすることが可能
相談者さんの希望する週3日勤務も上記(1号育短)で働く日数、曜日、時間をご自身で決め申請すれば病院はその通りの勤務にしなければなりません。
ご相談の中にある「19時間30分/週で、夜勤出来ない勤務」も可能です。
申請したものを拒否したり、ご相談内容のように別の制度に誘導する事はマタハラにもなります。そのようなことがあれば労働組合や労働局にある男女雇用均等室を活用し申請通りにするよう交渉又は仲裁に入ってもらいましょう。
Q1.現在育休中の看護師です。もうすぐ職場復帰をしますが、育短制度を利用したいと思っています。
労働組合のパンフレットhttp://www.zennisseki.or.jp/data/2017/pama2017s.pdfを見ましたが育短の申請時間を自分で決めると記載してあります。
家庭の事情もあり週3日勤務(2日間7時間45分、1日間4時間)=19時間30分/週で、夜勤出来ない(※1号育短)、この勤務で申請をしたいと考えています。
最近、病院の師長さんに呼ばれ面談した際に復帰後の勤務についての話になりこの希望を伝えると、師長さんから「当院は育短制度の6時間に短縮(※3号育短)しかしていない。夜勤もして貰わないと」と一方的に言われました。師長さんの言う通りにしないといけないのでしょうか?
A1. 育児短時間制度は大きく分けて3つの時間短縮制度と4つの勤務制限措置制度があります。この内容は全国の日赤施設で全社共通です。
例)看護師の場合(※交代制勤務者以外の方の場合は制度内容に少し違いがあるので注意)
時間短縮制度(下記の『1号育短』等の名称は分かりやすくするための通称であり、制度自体は育児休業規程第11条(1)の規程です)
(1号育短)1週間あたりの勤務時間が19時間30分から25時間までの範囲の勤務
(2号育短)始業または終業を1日を通じて2時間30分を超えない範囲で30分に短縮
(3号育短)1日の労働時間を6時間に短縮
勤務制限措置
①時差出勤
②所定労働時間を超えない勤務
③時間外勤務の制限
④深夜勤務の免除※左記以外でも上記育短1号で夜勤をしない申出をすることが可能
相談者さんの希望する週3日勤務も上記(1号育短)で働く日数、曜日、時間をご自身で決め申請すれば病院はその通りの勤務にしなければなりません。
ご相談の中にある「19時間30分/週で、夜勤出来ない勤務」も可能です。
申請したものを拒否したり、ご相談内容のように別の制度に誘導する事はマタハラにもなります。そのようなことがあれば労働組合や労働局にある男女雇用均等室を活用し申請通りにするよう交渉又は仲裁に入ってもらいましょう。

2019年01月25日
マタハラ被害に遭わないために知ってほしい、制度のこと③
昨年より、組合には病院で働く女性からの深刻なマタハラ被害の相談が相次いでいます。
正確な制度内容と活用方法を知り、おかしいな・・・と思ったら必ず組合にご相談下さい。
以下は、日本赤十字社の労働組合<全日赤>に寄せられた相談のひとつです。
事例③
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
相談>
正規職員です。育休明けで働き出して半年になります。
復帰前の予想より育児と仕事の両立ははるかに大変で、家庭の事情もあり、家族と相談し仕事を辞め子供が小学生に上がるまで育児に専念することになりました。
退職を上司に伝えたところ、上司から「育休から復帰して1年経たないで辞めるとなると、育休時に支払われた育児休業給は返して貰わなくちゃならないわよ」「1年間は頑張って」と言われました。
退職せず今のままで育児と仕事を両立することは出来ないので辞める選択肢しか無いのですが・・・。
復職後1年未満で退職したら育休時に支給された育児休業給等は返さないといけないでしょうか?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
答え>
育児休業給付金と育児休業給とは・・・
育児休業取得時に支払われる所得保障のことで、雇用保険から支給される育児休業給付金と、日赤職員には日赤が支給する育児休業給(二つの合計が賃金月額の80%)になります。
日赤職員の場合の支給要件は雇用保険の被保険者であり、育児休業の取得を行った者です。
育児休業を取得した場合に職員に支払われるものですので、育休終了後についての要件はありません。ご相談のケースのように事情で復職後1年未満で退職した場合でも返却の必要はありません。
又、育休終了時に予期せず家庭の事情等で復職が叶わず退職する場合もありますが、その場合でも一度支払われている給付金等を返却する必要はありません。
ご相談のケースは上司が制度を知らないでマタハラをしているか、もしくは、制度を知っている上で発言しているとすれば悪意がある重大なハラスメントにあたります。

正確な制度内容と活用方法を知り、おかしいな・・・と思ったら必ず組合にご相談下さい。
以下は、日本赤十字社の労働組合<全日赤>に寄せられた相談のひとつです。
事例③
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
相談>
正規職員です。育休明けで働き出して半年になります。
復帰前の予想より育児と仕事の両立ははるかに大変で、家庭の事情もあり、家族と相談し仕事を辞め子供が小学生に上がるまで育児に専念することになりました。
退職を上司に伝えたところ、上司から「育休から復帰して1年経たないで辞めるとなると、育休時に支払われた育児休業給は返して貰わなくちゃならないわよ」「1年間は頑張って」と言われました。
退職せず今のままで育児と仕事を両立することは出来ないので辞める選択肢しか無いのですが・・・。
復職後1年未満で退職したら育休時に支給された育児休業給等は返さないといけないでしょうか?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
答え>
育児休業給付金と育児休業給とは・・・
育児休業取得時に支払われる所得保障のことで、雇用保険から支給される育児休業給付金と、日赤職員には日赤が支給する育児休業給(二つの合計が賃金月額の80%)になります。
日赤職員の場合の支給要件は雇用保険の被保険者であり、育児休業の取得を行った者です。
育児休業を取得した場合に職員に支払われるものですので、育休終了後についての要件はありません。ご相談のケースのように事情で復職後1年未満で退職した場合でも返却の必要はありません。
又、育休終了時に予期せず家庭の事情等で復職が叶わず退職する場合もありますが、その場合でも一度支払われている給付金等を返却する必要はありません。
ご相談のケースは上司が制度を知らないでマタハラをしているか、もしくは、制度を知っている上で発言しているとすれば悪意がある重大なハラスメントにあたります。

2019年01月22日
マタハラ被害に遭わないために知ってほしい、制度のこと②
昨年より、組合には病院で働く女性からの深刻なマタハラ被害の相談が相次いでいます。
正確な制度内容と活用方法を知り、おかしいな・・・と思ったら必ず組合にご相談下さい。
以下は、日本赤十字社の労働組合<全日赤>に寄せられた相談のひとつです。
事例②
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
質問>
育休明けで復帰して1年になります。子供は2歳半で日々活発になっています。
院内保育所に預けて働いてきましたが、子供に外で遊んだり友達をたくさんつくって欲しいと市内の幼稚園に預けることにしました。
しかし、幼稚園の送り迎えが必要で少なくとも始業時30分、終業時1時間の就業時間の短縮が必要と分かりました。
『育児短時間勤務等に関する申出兼通知書』を上司に提出したところ、「育短制度は育休明けで復帰した時点で申し込まないと制度は取れない。働き始めて途中から申請しても無理」と言われ拒否されました。
そういった制度でしたか・・・?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
答え>
育児短時間制度は職員が小学校入学前の子(6歳に達する日以降の3月31日まで※育介法では3歳未満だが日赤は就学前まで)を育てるため一週間の所定労働時間を短くする制度です。
○働く日および時間帯を職員本人が決めることができ、施設はこれを承認しなければなりません。
○夜勤をする・しないの選択も職員本人が決めます。
ご相談のケースは正規の勤務時間の始めまたは終わりに1日を通じて2時間30分を超えない範囲で30分単位で短縮出来る(通称2号育短)の利用が可能です。
育短制度を利用したい場合は利用開始の1か月前までに届け出を行います。
利用する育短制度に依りますが期間は1回につき1か月から1年まで。子の就学前まで何度でも利用可能です。
*育短制度の中には一旦終了すると6か月間は取得出来ない制度もあるので注意しましょう。

正確な制度内容と活用方法を知り、おかしいな・・・と思ったら必ず組合にご相談下さい。
以下は、日本赤十字社の労働組合<全日赤>に寄せられた相談のひとつです。
事例②
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
質問>
育休明けで復帰して1年になります。子供は2歳半で日々活発になっています。
院内保育所に預けて働いてきましたが、子供に外で遊んだり友達をたくさんつくって欲しいと市内の幼稚園に預けることにしました。
しかし、幼稚園の送り迎えが必要で少なくとも始業時30分、終業時1時間の就業時間の短縮が必要と分かりました。
『育児短時間勤務等に関する申出兼通知書』を上司に提出したところ、「育短制度は育休明けで復帰した時点で申し込まないと制度は取れない。働き始めて途中から申請しても無理」と言われ拒否されました。
そういった制度でしたか・・・?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
答え>
育児短時間制度は職員が小学校入学前の子(6歳に達する日以降の3月31日まで※育介法では3歳未満だが日赤は就学前まで)を育てるため一週間の所定労働時間を短くする制度です。
○働く日および時間帯を職員本人が決めることができ、施設はこれを承認しなければなりません。
○夜勤をする・しないの選択も職員本人が決めます。
ご相談のケースは正規の勤務時間の始めまたは終わりに1日を通じて2時間30分を超えない範囲で30分単位で短縮出来る(通称2号育短)の利用が可能です。
育短制度を利用したい場合は利用開始の1か月前までに届け出を行います。
利用する育短制度に依りますが期間は1回につき1か月から1年まで。子の就学前まで何度でも利用可能です。
*育短制度の中には一旦終了すると6か月間は取得出来ない制度もあるので注意しましょう。

2018年11月13日
「日赤職員のための子の看護・家族の介護の手引き」完成
お疲れ様です。
今日は日赤職員が働きながら「介護」を行う際に活用出来る制度についてです。
この度、日赤の労働組合「全日赤(全日本赤十字労働組合連合会)」http://www.zennisseki.or.jp/から介護の制度や権利についての分かりやすいパンフレットが届けられました。
内容は----
<目次>
はじめに・・・・・p1
こどもの看護が必要な時・・・・・・p2
子の看護休暇の対象範囲・・・・・p3
家族の介護が必要なとき・特別有給休暇:介護休暇・・・・p4
介護休業規程・・・・p4
介護の対象家族の範囲・・・p5
「介護が必要」の基準について・・・・p6
介護休業の延長・撤回と介護休業請求の際の注意・・・・p7
働きながら介護する・所定労働時間短縮・・・・p8
所定労働時間を超えない勤務・・・・p8
時間外勤務の制限・・・・p9
深夜勤務の免除・・・・p9
看護休業中の賃金・・・・p10
職場からのよくある質問・・・・p10

パンフレットは熊本県医労連事務所にて無料で配布しています。
是非ご活用下さい!
今日は日赤職員が働きながら「介護」を行う際に活用出来る制度についてです。
この度、日赤の労働組合「全日赤(全日本赤十字労働組合連合会)」http://www.zennisseki.or.jp/から介護の制度や権利についての分かりやすいパンフレットが届けられました。
内容は----
<目次>
はじめに・・・・・p1
こどもの看護が必要な時・・・・・・p2
子の看護休暇の対象範囲・・・・・p3
家族の介護が必要なとき・特別有給休暇:介護休暇・・・・p4
介護休業規程・・・・p4
介護の対象家族の範囲・・・p5
「介護が必要」の基準について・・・・p6
介護休業の延長・撤回と介護休業請求の際の注意・・・・p7
働きながら介護する・所定労働時間短縮・・・・p8
所定労働時間を超えない勤務・・・・p8
時間外勤務の制限・・・・p9
深夜勤務の免除・・・・p9
看護休業中の賃金・・・・p10
職場からのよくある質問・・・・p10

パンフレットは熊本県医労連事務所にて無料で配布しています。
是非ご活用下さい!
2018年10月30日
マタハラ被害に遭わないために知ってほしい、制度のこと
今年度に入り、組合には病院で働く女性からの深刻なマタハラ被害の相談が相次いでいます。
正確な制度内容と活用方法を知り、おかしいな・・・と思ったら必ず組合にご相談下さい。
以下は、日本赤十字社の労働組合<全日赤>に寄せられた相談のひとつです。
事例①
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
妊娠が判明しましたが、体調が悪く医師の診断では「母健連絡カード(※母性健康管理指導事項連絡カード)」に自宅療養を要す旨の記載を受けました。
職場の上司にカードを渡し、休業を申し出ましたが「当院で受診した場合にのみ休業は認められる。他院で受診したこのカードでは申請を受け付けられない」と言われました。
変だと感じましたが、無理して働いた結果流産しました。
ショックが大きく、この病院ではもう働き続けられないと思っています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎母健連絡カードとは・・・
母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)は、行政が発行する医師等からの女性労働者への指示事項が適切に事業主(会社側)に伝達されるためのツールです。
主治医は、妊娠者等が健康診査等の結果、通勤緩和や勤務時間短縮、自宅療養等の指導事項がある場合、必要な事項を記入します。
働く女性(正規・非正規問わず)からカードが提出された場合、事業主は「母健連絡カード」の記入事項に従って通勤緩和や勤務時間短縮等の措置を講じなければなりません。
このように妊婦に対し適切な措置を講じることは、(母健連絡カードの提出の有無にかかわらず)事業主(会社側)の義務です。
母健連絡カードは、一般の傷病での診断書と同等に取り扱っていただくものです(しかも、診断書よりも安価で書いていただくようにと、病院等へは指導されています)。
ですから、診断書の提出はせずとも、母健連絡カードの提出で自宅療養が認められるべきなのです。
(厚労省/(財)女性労働協会HPより抜粋)
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/senmon/senmon19.html
正確な制度内容と活用方法を知り、おかしいな・・・と思ったら必ず組合にご相談下さい。
以下は、日本赤十字社の労働組合<全日赤>に寄せられた相談のひとつです。
事例①
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
妊娠が判明しましたが、体調が悪く医師の診断では「母健連絡カード(※母性健康管理指導事項連絡カード)」に自宅療養を要す旨の記載を受けました。
職場の上司にカードを渡し、休業を申し出ましたが「当院で受診した場合にのみ休業は認められる。他院で受診したこのカードでは申請を受け付けられない」と言われました。
変だと感じましたが、無理して働いた結果流産しました。
ショックが大きく、この病院ではもう働き続けられないと思っています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎母健連絡カードとは・・・
母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)は、行政が発行する医師等からの女性労働者への指示事項が適切に事業主(会社側)に伝達されるためのツールです。
主治医は、妊娠者等が健康診査等の結果、通勤緩和や勤務時間短縮、自宅療養等の指導事項がある場合、必要な事項を記入します。
働く女性(正規・非正規問わず)からカードが提出された場合、事業主は「母健連絡カード」の記入事項に従って通勤緩和や勤務時間短縮等の措置を講じなければなりません。
このように妊婦に対し適切な措置を講じることは、(母健連絡カードの提出の有無にかかわらず)事業主(会社側)の義務です。
母健連絡カードは、一般の傷病での診断書と同等に取り扱っていただくものです(しかも、診断書よりも安価で書いていただくようにと、病院等へは指導されています)。
ですから、診断書の提出はせずとも、母健連絡カードの提出で自宅療養が認められるべきなのです。
(厚労省/(財)女性労働協会HPより抜粋)
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/senmon/senmon19.html
2017年05月26日
育児休業制度について(17年度)
こんにちは。
今日は、まだまだ組合に相談の多い出産・育児関係の権利です。
組合では女性職員はもとより男性職員の育児休業取得を促進する立場で応援しています!
⦿育児休業制度(日赤育児休業規程95.4.1全日赤協定)
3歳に満たない子を養育する職員は、男女問わず、希望する期間子供を養育する為に休業することができます。※子は実施および養子・里親制度含む
⦿育児休業を取るための手続き
育児休業を取得する場合は、育児休業の開始予定日の1ヶ月前までに「育児休業等に関する申出書」を施設に提出します。
⦿育児休業を変更するとき
①育児休業の撤回は、開始予定日の前日まで申し出ることが出来ますが、特別な事情を除き、撤回後にその子の育休の申出はできません。
②開始予定日の変更は、前日までに申し出ることで1回に限り予定日より前の日に変更する事が可能です。
③終了予定日の変更は、1ヶ月前(特別な場合は2週間前)までに申し出ることで1回に限り予定日より後の日に変更する事が可能です。
※終了予定日前への変更は認められていません。上司が「早く出てきて」と云った場合も、逆に労働者が「早く出たい」と云った場合もどちらも認められません。
④次の場合には育児休業は終了となります。特別な場合を除き、終了後にその子の育休の申出はできません。
・当該職員が産前産後休暇、介護休業、新たな育児休業が始まったとき
・その子が死亡、その他養育しなくなったとき
・その子が当該職員の子でなくなったとき
・その子が3歳になったとき
・育児休業期間が終了したとき
今日は、まだまだ組合に相談の多い出産・育児関係の権利です。
組合では女性職員はもとより男性職員の育児休業取得を促進する立場で応援しています!
⦿育児休業制度(日赤育児休業規程95.4.1全日赤協定)
3歳に満たない子を養育する職員は、男女問わず、希望する期間子供を養育する為に休業することができます。※子は実施および養子・里親制度含む
⦿育児休業を取るための手続き
育児休業を取得する場合は、育児休業の開始予定日の1ヶ月前までに「育児休業等に関する申出書」を施設に提出します。
⦿育児休業を変更するとき
①育児休業の撤回は、開始予定日の前日まで申し出ることが出来ますが、特別な事情を除き、撤回後にその子の育休の申出はできません。
②開始予定日の変更は、前日までに申し出ることで1回に限り予定日より前の日に変更する事が可能です。
③終了予定日の変更は、1ヶ月前(特別な場合は2週間前)までに申し出ることで1回に限り予定日より後の日に変更する事が可能です。
※終了予定日前への変更は認められていません。上司が「早く出てきて」と云った場合も、逆に労働者が「早く出たい」と云った場合もどちらも認められません。
④次の場合には育児休業は終了となります。特別な場合を除き、終了後にその子の育休の申出はできません。
・当該職員が産前産後休暇、介護休業、新たな育児休業が始まったとき
・その子が死亡、その他養育しなくなったとき
・その子が当該職員の子でなくなったとき
・その子が3歳になったとき
・育児休業期間が終了したとき
2017年03月15日
「育児短時間」制度等の利用について
春の兆しが見えたと思った矢先の寒さ再到来。
今週末からは暖かくなる予報ですが、待ち遠しいかぎりです。
さて、本日は「育児短時間」制度等の利用についてです。
出産後、育児休業等を終えて職場復帰する際に、「育児短時間勤務制度(育短)」を利用する職員が増えています。
それにともない、組合に相談も寄せられていますのでよくある質問にお答えしたいと思っています。
相談>「育短」勤務中です。日勤の職員より2時間早く帰ることになっていますが、なかなか決められた時間には帰れず、通常の日勤の終業時間まで残って働くこともあります。
時間外手当の取り扱いはどうなりますか?
回答>原則として「育短」制度は残業をさせてはならないことになっています。
これは日赤本社と全日赤(労働組合)の交渉でも確認を取っており、日赤本社も「育短者に残業をさせてはならない」「そのような実態があるなら指導する」と言っています。
しかしながら現場は忙しすぎて指定の時間に帰ることができず、残って仕事をしてしまうことは少なくありません。
育短中の賃金は、短縮された勤務時間数で計算され支給されることになっているので、そもそも常勤者との賃金に差があります。
ですので残って働いた時間分の賃金は時間外勤務の申請をしなければ保障されません。
面倒でも、残業をした場合はきちんと申請するようにしましょう。
※通常日勤の終業時間までなら100/100の扱いで保障されます。
また、夏や冬のボーナス(一時金)額はもともと短縮されている時間が232時間30分(7時間45分×30日)を超えていると超えた時間分が在職期間から減算されることになっています。<勤務しなかった時間の合算が30日超えた場合に当該超過期間を在職期間から除算されている。
この在職期間は一時金の算定にも影響しますので、育短者が時間外申請をするかしないかで毎月の給料に加えて、一時金の支給額も変動するということになります。
育短者が指定した時間以外の労働を行った場合は必ず申請しましょう。
◇全日赤から「妊娠・出産・子育ての手引き:パパ・ママパンフ」改訂版発行されています。
日赤は女性の多い職場だからこそ妊娠・出産・育児に対する制度が充実しています。
しかし複雑な制度もあり管理者が誤った運用を行っていることも多々あります。
正確に利用する為にも制度を正確に知りたいですね。
先だって、全日赤本部から発行された2017年度の「妊娠・出産・子育ての手引き:パパ・ママパンフ」改訂版がかなり見やすいのでそれも参考に下さい。
http://www.zennisseki.or.jp/data/2017/pama2017s.pdf
今週末からは暖かくなる予報ですが、待ち遠しいかぎりです。
さて、本日は「育児短時間」制度等の利用についてです。
出産後、育児休業等を終えて職場復帰する際に、「育児短時間勤務制度(育短)」を利用する職員が増えています。
それにともない、組合に相談も寄せられていますのでよくある質問にお答えしたいと思っています。
相談>「育短」勤務中です。日勤の職員より2時間早く帰ることになっていますが、なかなか決められた時間には帰れず、通常の日勤の終業時間まで残って働くこともあります。
時間外手当の取り扱いはどうなりますか?
回答>原則として「育短」制度は残業をさせてはならないことになっています。
これは日赤本社と全日赤(労働組合)の交渉でも確認を取っており、日赤本社も「育短者に残業をさせてはならない」「そのような実態があるなら指導する」と言っています。
しかしながら現場は忙しすぎて指定の時間に帰ることができず、残って仕事をしてしまうことは少なくありません。
育短中の賃金は、短縮された勤務時間数で計算され支給されることになっているので、そもそも常勤者との賃金に差があります。
ですので残って働いた時間分の賃金は時間外勤務の申請をしなければ保障されません。
面倒でも、残業をした場合はきちんと申請するようにしましょう。
※通常日勤の終業時間までなら100/100の扱いで保障されます。
また、夏や冬のボーナス(一時金)額はもともと短縮されている時間が232時間30分(7時間45分×30日)を超えていると超えた時間分が在職期間から減算されることになっています。<勤務しなかった時間の合算が30日超えた場合に当該超過期間を在職期間から除算されている。
この在職期間は一時金の算定にも影響しますので、育短者が時間外申請をするかしないかで毎月の給料に加えて、一時金の支給額も変動するということになります。
育短者が指定した時間以外の労働を行った場合は必ず申請しましょう。
◇全日赤から「妊娠・出産・子育ての手引き:パパ・ママパンフ」改訂版発行されています。
日赤は女性の多い職場だからこそ妊娠・出産・育児に対する制度が充実しています。
しかし複雑な制度もあり管理者が誤った運用を行っていることも多々あります。
正確に利用する為にも制度を正確に知りたいですね。
先だって、全日赤本部から発行された2017年度の「妊娠・出産・子育ての手引き:パパ・ママパンフ」改訂版がかなり見やすいのでそれも参考に下さい。
http://www.zennisseki.or.jp/data/2017/pama2017s.pdf